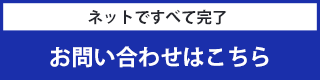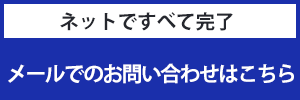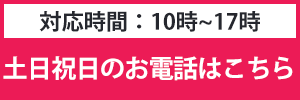筆跡鑑定人の選び方
裁判で棄却された。一審敗訴。その理由、ご参考になれば幸いです。
筆跡鑑定は信頼性に欠ける。それはWeb上無数にいるエセ鑑定人の鑑定書だから、本物の鑑定人はこんな人
実際に「裁判所からの嘱託」「警察からの嘱託」を受けている法科学鑑定研究所がご説明いたします
筆跡鑑定人の選び方
当社で取り扱う筆跡鑑定とは「科学的筆跡鑑定法」(法廷等に対応する物)を指します。
あくまで公の『証拠』として扱われる物だけを取り扱っています。

なぜ人は似非筆跡学にだまされるのか?
筆跡鑑定は、書き手の個性を示すものであり、犯罪捜査などで有用な情報を提供することができます。しかし、似非筆跡学による鑑定は、科学的に検証されていない方法であり、信頼性に欠ける可能性があります。
人々が似非筆跡学にだまされる理由は、主に2つあります。
1つは、一般的な知識や情報に乏しいことが挙げられます。似非筆跡学について詳しく知らない人々は、その方法が科学的に検証されていないことを知らず、信頼性についても正しく判断することができません。また、ホームページなどで紹介されることが多く、一部の人々からは、一種の「スピリチュアルなもの」として捉えられることもあります。
もう一つの理由は、相談者の人物が望む結果に寄せて受検することです。例えば、特定の書類に対して疑問を持っている場合、その署名や手紙の筆跡に問題があるように見えることがあります。そのような場合、似非筆跡学者は、営業行為を理由に、相談者の人物に都合の良い検査結果を示すことがあるということです。
つまり、彼らは相談者からお金をもらうための道具として鑑定を利用しています。そのため相談者の要望に応えるため、商売をするために、客観的な判断をすることができず、正しい鑑定結果を出すことができません。このような営業行為は、客観的な鑑定を妨げる要因となるため、似非筆跡学の信頼性に大きな影響を与えます。
総じて言えることは、似非筆跡学による鑑定は、科学的に検証されておらず、信頼性に欠ける可能性があるということです。正確な筆跡鑑定を行うためには、科学的な方法を用いた公平で正確な鑑定が必要です。また、人々が知識を持ち、望む結果に影響を受けないようにすることが重要です。
次項では、鑑定とは何か、どのような人物が筆跡鑑定を行うのか、確認してみましょう。
鑑定人の定義
【鑑定】かんてい
大辞林 第二版 (三省堂)
(1) 科学的な分析や専門的な知識によって判断・評価すること。
(3)〔法〕 訴訟において、裁判官の判断を補助するため、裁判所が指名した学識経験者に専門的知識・判断を報告させることを目的とした証拠調べ手続き。
【学識経験者】がくしき-けいけんしゃ
大辞林 第二版 (三省堂)
専門領域の学問で評価を受け、豊富な経験と高い見識をもつと社会的に認められる人。
【学問】がくもん
(WikiPedia)
学問(がくもん)とは、文化の1つで、系統的・体系的知見の総体である。学問の専門家を一般に「学者」と呼ぶ。
現在、ある学問が存在すれば、一般的には、それに関連する学会が(ひとつ乃至複数)存在しており、その学問の発展に関与しており、 各学者は一般的には、当該学問のいずれかの学会の(多くは複数の学会の)会員となっていて、自身の研究の成果を発表することで認知を得たり、 あるいは他の学者の発表を確認することで当該学問の最新の情報を把握し、自身の研究に役立てようと努めている。
日本の学問体系は各種学会を統合する「日本学術会議」もしくは2001年に設立された「総合科学技術会議」のいずれかに組織化されています。
「筆跡鑑定」は自然科学分野の学問に属し「日本法科学技術学会」に所属する法科学者により研究が行われています。
専門領域の学問で評価を受け、豊富な経験と高い見識をもつと社会的に認められる方に、専門的知識・判断を報告させることを「鑑定」といいます。
そして、このようなの方々を「鑑定人」と呼ぶのです。
では、どのような基準で鑑定人を選べばよいのか次項ご説明します。
鑑定人の基準とは
アメリカの法廷では「証拠として採用する基準」を設けています。
筆跡鑑定書も例外なく審査を受け、証拠となるものなのか否かが問われます。
【1993年ドーバート対メレル・ダウ製薬の裁判で示された科学的証拠の許容性基準】
これをドーバート基準と呼ばれ、陪審員制をとるアメリカでは、新規の科学鑑定を法廷で採用するか否かを裁判官がゲートキーパーとして判断する仕組みになっています。
この仕組みは疑似科学を見分ける役割も兼ね備えています。
【ドーバート基準は以下の4点】
1)理論や方法が実証的なテストが可能なこと。
- 仮説が実験テストなどにより、科学的根拠があること
- 判定のデータを開示し、第三者が同じ判定結果にならなければ認められません
(◎ 再現性ある検査方法による数式・数値を用いた結論)
(☓ 思い込みや勘など人の判断にり結果が変わる理論)
2)理論や技術がピア・レビューされあるいは出版されていること。
- 理論や技術が学会など科学者のコミュニティーで点検させていること
- 理論が学会に論文として発表され、科学者の点検を受けた理論であること
(◎ 学会に論文として発表され専門家に点検された理論である=科学者)
(☓ 独自理論や自己流は、科学的方法論に基づいていないため正確さに欠ける=自称専門家)
3)結果を評価するために誤差率や標準的な手法が明らかにされていること。
- 分析的基準が決められ、それがどの程度の誤りが生じるのか明らかにされている
- 数値や確率には理論的根拠を示し、結果を証明しなくてなりません
(◎ 基準に基づく分析は、精度が高く信頼性が高いため、結果が正確であることが保証されます=科学)
(☓ 判定基準や判断方法などを示さず、根拠のない信念や主張を追求すること=疑似科学)
4)専門分野で一般的に受け入られていること。
- 学会などにおける受容の程度が考慮されます
- どの学会の、どの研究者達が、どう判定して、その結果、どのような評価なのか
(◎ 筆跡鑑定をあつかう学術団体=法科学技術学会)
(☓ 学会や科学界では受容されない証拠や実験が存在しない独自の非科学理論=自称鑑定人)
日本でも刑事訴訟での裁判では、このドーバート基準による鑑定書の審査が行われる事もあります。
つまり、裁判官は提出された鑑定書をこの基準で捉えています。
ですから、一般の方で筆跡鑑定が必要と考え鑑定人を選ぶ場合、この基準が有効になります。
法科学鑑定研究所の筆跡鑑定人
訴訟における鑑定人は、一定の事実につき自己が過去に得てきた学識経験など、専門的知見に照らし客観的な意見を述べることが要求されます。
鑑定人は裁判官の心証形成作業を一部補完する役割を担っており、すなわち、裁判官同様に原告・被告何れの立場にも依らない中立の精神で案件に臨む姿勢が要求されるのです。
鑑定書とは鑑定人による強い意見書です。鑑定人は、一般的な学者ではありません。専門性の高い見識と実績を持ち、訓練を受けている方々です。
鑑定書は論文や報告書ではありません。法廷で誤解なく適応する文章作成能力と理論的な結論が求められます。
科学的な解析能力 + 理論的な思考能力 = 「法科学者」、当社の鑑定人はこの訓練を受けています。
ですから、当社の鑑定人は、裁判に強いのです。
自称鑑定人と本物の鑑定人を見分ける方法
自称鑑定人と本物の鑑定人を見分けるためには、以下のようなポイントに注目することが重要です。
鑑定方法の正確性
本物の鑑定人は、正確な鑑定結果を出すために、適切な方法論や専門知識を持っています。自称専門家は、情報や意見が正確でない場合があります。自称鑑定人がどのような方法で鑑定を行っているのか、鑑定の方法やプロセスに疑問がある場合は、詳細な説明を求めることが重要です。
学歴や実績の有無
本物の鑑定人は、専門分野に関連する学歴や実績を持っています。また、専門的な論文や著書を発表していることもあります。自称鑑定人がどのような学歴や実績を持っているのか専門的な論文や著書を確認することが重要です。
経験の有無
本物の専門家は、長年にわたってその分野で経験を積んできています。経験に基づく知見や洞察力があります。自称鑑定人がどのような経験や実績を持っているのか、過去にどのような鑑定を行ったことがあるのかを確認することが重要です。
評判や口コミの確認
学術団体が発表する論文サイトや判例タイムなどの専門誌、インターネット上の評価サイトなど、信頼できる情報源からの評価を確認します。
鑑定結果の妥当性
自称鑑定人が出した鑑定結果が、その分野で一般的に認められている結果と合致するかどうかを確認することが重要です。
鑑定人のプロフィールの確認
鑑定人の名前や所属団体、連絡先などのプロフィールを確認することで、本物の鑑定人である可能性が高いかどうかを判断することができます。
これらのポイントに注目することで、自称鑑定人と本物の鑑定人を見分けることができます。また、鑑定を依頼する場合は、信頼できる鑑定人に依頼することが大切です。
Copyright(C)Analysis Laboratory of Forensic Science, Inc. / 法科学鑑定研究所株式会社